【記事】アドベンチャーレースを始めるには?最低限これだけおさえよう!初心者必須のレース知識 後編
ゆるやま!まつもとです。
アドベンチャーレースをはじめたい!という方にお送りする初心者必須のレース知識後編です。前編では基本ルールと、必要なアイテムについて解説しました。
後編では「地図読みとかどうすればいいの?」とか「どのくらい走れればいいの?」といった技術、体力について解説します。

この記事はあくまでゆるやまの主観で、レースに初めてチャレンジするなら、という基準で書いています。
レース内容や天候などの状況により難易度は大きく変わります。あくまで参考として、これがクリアできれば安全を保証する、というものではないので、最後はご自身で判断してくださいね。
走力、体力はどのくらい必要?
アドベンチャーレースは長くてシンドくてキツい。そんなイメージがありますが(そして概ねそのとおりなんですが)、じゃあどのくらい体力があればレースに出られるの?というのはなかなか判断が難しいところだと思います。
レース経験者がいう「とりあえず出てしまえばどうにかなるよ!」というのも一理あって、マラソン経験がなくても完走できる人もいれば、日常的に運動している人でもバテてしまったりとやってみないと分からない、というのも正直なところです。
ただそれだとレース前にどれだけ練習していいかわからないよ!と思ってしまうのもその通り。今まで参加した人の体力、経験などから、とりあえずこれくらいできればレースを楽しめるだろうという基準を、ゆるやま的観点で解説します。
例えば40kmくらいのレースであれば、このくらいをひとつの基準にしてみてください。
- ランニングであれば10km前後をゆっくりのペースでいいので走りきれる
- 最大標高差1200m以上、行程10km以上の登山を問題なくこなせる
- または低山で、行程20km以上の登山を問題なくこなせる
アドベンチャーレースで完走を目指すには速く動く能力よりも、多少ペースを下げてでも長時間動き続ける能力のほうが重要です。レース中ずっと走り続ける必要はないので、10kmのランニングをひとつの基準としてみました。
参考として、ゆるやまが初参加のレースで初完走したとき、ハーフマラソンがだいたい2時間くらいでした。40kmのレースであれば、20kmを走れる人なら体力が問題になることはあまりないはずです。
登山を日常的にこなしている人もレースに強いイメージです。参考例の最大標高差1200m、行程10km以上というと、谷川岳西黒尾根ルートや、会津駒ケ岳滝沢ピストンなど一般的な百名山の登山と思ってください。または標高差500mくらいの低山でも20kmを超える行程を日帰りできる人なら特に問題はないかと思います。
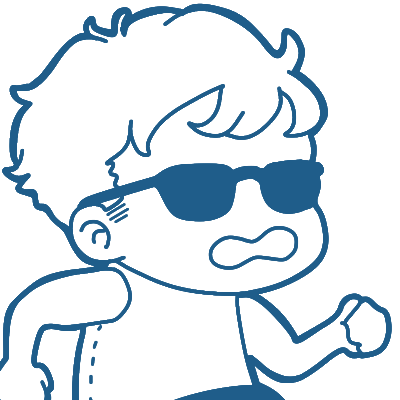
個人的には走力、体力といっても、水平方向の移動と垂直方向の移動は別ジャンルと思っています。
アドベンチャーレースはどうしても山岳地帯が主戦場になるので、普段ランニングをメインしている人は階段昇降などの垂直方向への移動の練習を取り入れるとレースが楽になりますよ。
前提条件として、体力があればあるほど安全、かつレースでは有利なので、可能であれば継続的な運動習慣を心がけましょう。そのほうがレースだけでなく健康面でもハッピーなのは間違いありません。
登山向けの体力づくりや走り方はプロの書籍を参考にしてね!
地図やコンパスの使い方の基本
基本的な地図読み対策については、上の3本の動画で解説しているのでそちらをご覧ください。
地図読みはアドベンチャーレースの醍醐味のひとつであり、それだけで分厚い本が何冊もかける奥深い分野です。そして自分が多くを語れるほど専門的な知識を持っていないこともあります。
動画をちゃんとみてもらえれば基礎的なイメージはつかめるようになっていますが、あくまで基本概念を伝えることをメインに置いているので、さらに学びたい!という方はやはりプロの書籍で学ぶことをオススメします。

アドベンチャーレースでは正直、確実なナビゲーションができるチームメイトがひとりでもいるなら、全員が地図を読める必要はありません。
ただ主体的にルートを決めたり、みんなでルートを考えていくのもアドベンチャーレースの醍醐味です。地図が読める、読めないでレースの楽しさは全然変わるので、ぜひ地図読みを楽しんでもらえればと思います。
地図読みを実践したい!どうしたらいいの?
地図を持って山に入るだけでも練習にはなるのですが、登山道を離れると危険だったり、そもそも自分のナビゲーションが正しいのか間違っているのか判断がつかなければ練習にならない、というケースもよくあります。
そういった方にオススメなのがオリエンテーリングと、地図読み講習です。
オリエンテーリング
オリエンテーリングはアドベンチャーレースのラン、トレッキングセクションのナビゲーションのみに特化したような競技です。というかオリエンテーリングのほうが起源は古いスポーツなので、そのゲーム性をアドベンチャーレースでも流用しているといったほうが正しいかもしれません。
オリエンテーリングの大会は上級者だけなく全くの初心者でも参加できる大会が多く存在します。週末にポケットマネーで参加できるような小規模な大会も多く、読図に興味がある方はぜひ一度参加してみてください。
ちなみに自分はノリで京葉OLクラブに入会しています。首都圏にお住まいで興味のある方はぜひ(あまり運営に貢献できてなくてすみません…)
オリエンテーリングは地図の精度を何よりも大切にしているので、地図側が間違っていたせいでルートをロストするといったケースがほとんどありません。地図を完全に信頼できる環境というのは実はなかなかないので、一度体験してみることをオススメします。
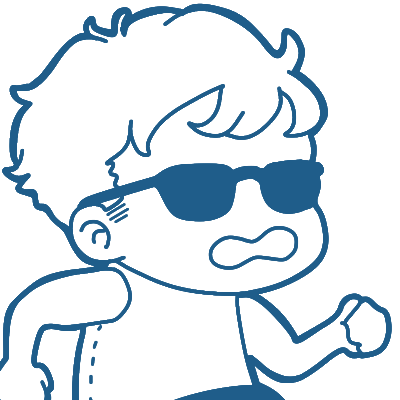
国内のアドベンチャーレースでは主に、1/25000の国土地理院の地図を使用します。登山でよく使う山と高原の地図が1/50000なのでそれよりはいくらか詳細ですが、どうしても等高線で書ききれない凹凸があったり、微妙な地形が抜け落ちていたりします。
周囲の地形から「地図ではこうだけど実際はこう」みたいな予想をする必要が出てくるので、どうしても実地での経験が必要です。
その点オリエンテーリングは1/10000より詳しい地図がほとんどなので、ほぼ寸分の狂いなく記載されており、地図を信じて歩いてまず問題ありません。
地図読み講習会
アドベンチャーレースだけでなく、登山、オリエンテーリング、ロゲイニングなどに向けて、日本全国で地図読みの講習会が開かれています。
基本的な地図の見方、コンパスの使い方から始まり、実際にフィールドに出てどう地図をみるのかというのを体験できる貴重な機会なので、ぜひ参加してみてください。
レース・講習情報はこちら
https://yuruyama.info/category/raceinfo/
MTB対策
マウンテンバイク対策については、レースによって習得するべき内容が変わってきます。
例えばエクストリームシリーズなどではそこまで本格的なダウンヒル(MTBで山道を降りる)が求められるケースは少なく、自転車に乗れれば特に問題がない場合がほとんどです。
参加したいレースの過去の情報を調べて、ダウンヒルなど危険度の高い走行を練習する必要があれば講習、スクールなどの受講をオススメします。
ただしどのレースにおいてもMTBでかなりの距離を走ることになるので、対自転車力はつけておいたほうが無難です。自分はたいがいMTB区間で体力を削られています…

トライアスロンをやっていたり日常的にロードバイクに乗っている人はそれだけでかなりアドバンテージがあります。
また動画でも触れていますが、半分くらいのセクションでMTBに乗るのではなく乗られる(担ぐ)ことが多かったりするので、MTBを担ぐという(おおよそアドベンチャーレース以外では一生使うことのない)技術を身につけておくと、本番で焦らないかも知れません。
パドルスポーツ対策
こちらもレースによって対策は変わります。
国内レースでは安全対策の問題などからパドルセクション自体が存在しないレースも多く、その場合にはもちろん練習する必要はありません。
アドベンチャーレースで採用されるパドルスポーツは一般的に下記のようなものがあります。
- カヤック
- カヌー
- パックラフト
- ラフティング
- SUP
大会要項に必ず記載があるので、未経験のものがあれば一度講習を受けておいたほうが無難です。
どの艇に乗るとしても、PFD(ライフジャケット)の装着は必ず義務付けられており、レースでも厳しいチェックが入ります。
初めてレースに参加する人でまったく一度もどの艇にも触れたことがない、という人をたまにみかけますが、徒歩と違い水は簡単に人の命を奪います。
初心者講習やツアーでもいいので必ず一度はパドルスポーツに触れてから、レースに参加することを強くオススメします。
ラフティングやカヤックを楽しもう!
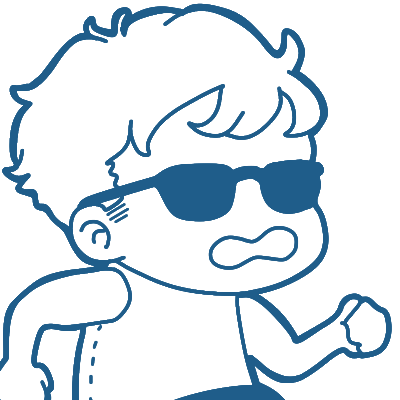
自分はどちらかというとなんでも独学で突き進んでしまうタイプで、地図読みもそのほとんどを書籍とソロ登山のなかで身につけました。
ただ水物に関しては初心者が自力で習得する、というのはなかなか無理があるので、諦めて(?)習うことをオススメします。
最後に
アドベンチャレースに出てみたい、という方に向けて、今伝えられる情報を全力でお届けしてきました。
実際には体力がなくても、地図読みの基本を勉強していなくても、カヤックに乗ったことがなくてもレースには出られます。出られるか出られないかで言えばそうなんですけど、その結果本当の意味でレースを楽しめないまま、ツラい思い出となって二度と出たくない、という人がいるのも事実です。
いろんな人に参加してほしい、体力技術関わらず体験して欲しいと思う反面、レースの特性上絶対安全とは言い切れず、レースや登山、各スポーツの経験者が暗黙の了解として認識していることも、一般的には「そんなこと知らなかった」というようなことも多く存在します。
危険を楽しむことだけがアドベンチャーレースではありません。どこまで準備をして万全の体制でレースに挑めるか、その上で「ままならない」ことにどう対処していくのか、そういった姿勢がレースの大事な要素であり、長く楽しんでいく上で重要だと個人的には考えています。
前編、後編で本当に長くなりましたが、正直これでも情報量として足りないよ、と突っ込まれるレベルだと思います。レースに参加したい人のハードルをあげたくはない、でも情報発信をするからには無責任に危険な行為を薦めるわけにはいかない、という狭間で執筆しましたのでそのあたりはいい具合に感じ取ってもらえれば嬉しいです(笑)
ということでゆるやま!まつもとがお送りする「アドベンチャーレースを始めるには?最低限これだけおさえよう!初心者必須のレース知識」でした。どこかの会場でお会いできることを楽しみにしています。ではまた。

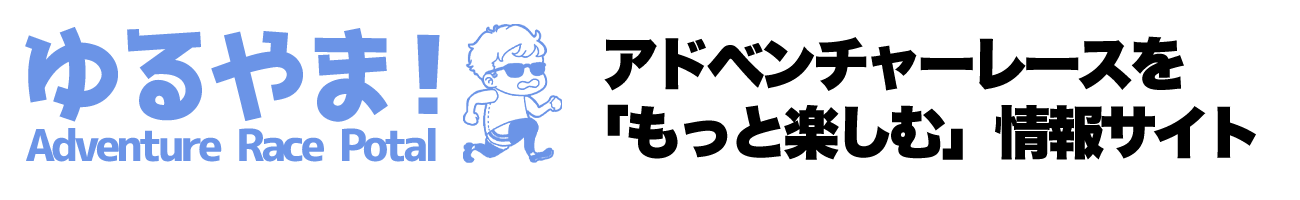



“【記事】アドベンチャーレースを始めるには?最低限これだけおさえよう!初心者必須のレース知識 後編” に対して1件のコメントがあります。